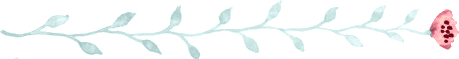スーパーでローストチキンを買った。クリスマスっぽいシールがついたパックのやつだが、どうみても鶏の照り焼きで、醤油っぽくてらてら光っている。そのいかにも庶民的な風情に満足してスーパーを出ると、5分くらい歩いたところにあるケーキ屋に行ってホールケーキを買った。最近はいろいろあるみたいだけど、生クリームのいちばんオーソドックスなのを選んだ。ケーキ屋自体も特に有名な店ではなくて、ただ普通に近所で浸透しているだけのところだから、あんまりおいしくはないかもしれない。
それから少し考えて、もう一度スーパーに戻った。よく考えたらチキンとケーキだけでは食卓がさみしい。とりあえずポテトサラダと、オーブンで温めるタイプのアルミ容器入り冷凍グラタン、それからポタージュスープの素を買った。それぞれに(ポテトサラダにさえ)数種類あったけど、どれもいちばんなんでもなさそうなものを選んだ。
あのひとは、今日も仕事だった。クリスマス休暇は既婚者に譲ったのだろうと思う。ベッドの中であのひとが着替えたりネクタイを締めたりする気配を感じていると、不意に声が降ってきた。
「いつもより早く帰れると思うから、」
思うから、なんなのかは言わないまま、誤魔化すように小さく笑うとあのひとは家を出た。
買ったものをとりあえず冷蔵庫と冷凍庫に入れ、テレビをつけると外国のクリスマスの様子を紹介する番組だった。きらきらした髪の小さな女の子が雪道をあるいている。まんまるに着膨れて、ほっぺたを紅くしている。父親が手を引いている。その隣に母親が居て、ふわふわとあったかそうな布に包まれた赤ん坊を抱いている。楽しげに言葉を交わすたびに、白い息が零れる。
チャンネルを変えた。歌番組だった。スーパーでも流れていたラスト・クリスマスを、よく知らないアイドルが歌っている。クリスマスソングのメロディーは、なんとなく人を焦らせる効果があるような気がする。もうクリスマスだなんて信じられない!まだ私はクリスマスを迎えられないのに!なんにも準備ができてないのに!ああクリスマスが来てしまう!
手近にあった布をがばっと被った。視界が全部薄オレンジになった。自分が被ったのは膝掛け用に使っている毛布らしいと気付き、この際寝ることにする。手探りでリモコンを操作し、テレビを消す。アイドルの声は途切れても、まだ頭にぐるぐるとラスト・クリスマスが渦巻いて、心はざわざわ焦っていた。目を瞑って耐える。波が引くのをやり過ごすようにじっとしていると、やがて眠くなってきた。意識を失うまで、たぶん15分もなかっただろう。
途中、なにかオレンジっぽい色合いの夢を見たように思うけど、目覚めた瞬間に忘れてしまった。夕焼け色の毛布のせいかもしれない。薄明るくて、あったかくて、さみしい、いかにも毛布っぽい質感の夢だった気がする。
目を覚ますと、部屋は薄暗かった。まだ明りのいらない時間に寝入って、もう日が呉れようとしているらしい。西日が差し込んで、部屋全部が夕焼けに染まっているような感じだった。もぞもぞと立ち上がって電気を付ける。白熱灯は夕暮れの光とかんぜんに溶け合った。
あのひとはまだ帰っていない。
大したものは買わなかったから、夕飯の用意はあのひとが帰ってからでじゅうぶんだろう。
――それまで何をしていよう?
明るくした部屋を見回しても、なにも思い浮かばない。しばらくは何をするでもなくオレンジの毛布の端をもてあそんでいた。ほつれた糸を玉結びにしてみたり、しょちゅうかぶっているせいで毛羽立った表面をなでつけてみたり、ラスト・クリスマスをくちずさんでみたり。アイ・ゲイブ・ユー・マイ・ハート。全体的にうろ覚えの歌詞で、たぶん一番たしかな記憶がこの部分だ。直訳すれば、私はあなたに私のこころをあげました。あるいは、私はあなたに心臓をあげた。もうちょっと踏み込めば、私の愛はあなたに捧げたのに。それともこうかな。ハートはあなたにあげてしまったから、私の胸にはないのです。
こんなことをつらつら考えていたものだから、ラスト・クリスマスがとまらなくなって困る羽目になった。鼻歌をやめても頭の中で同じ部分だけが延々と流れている。I gave you my heart!
――早く帰ってこないかな。
いらいらしてきた。何もすることがないのがいけない。でも今日と言う日は一年のうちもっとも一人で暇を潰しにくい日じゃないだろうか。クリスマスに独りでいてはいけないわ。そんな台詞をなにかの映画で聞いた覚えがある。聞いたときはひとの勝手じゃないかと思ったものだけど、今日は駄目だった。今年のこの日の自分は、なぜだろう、胡散臭いキリスト教っぽい愛に洗脳されている。今日は家族と談笑せねばならない。独りで本なんか読み始めちゃいけない。そんなことはしたくない。だってあのひとが帰ってくる!自分は帰りを待っているんだから!
――だけど帰ってこなかったらどうしよう。
ちらっと、頭をよぎる。ちらっとだけど、何度もよぎる。頭の中を高速で縦横無尽に駆け回っている。でもこの考えはじぶんのなかで禁則事項なので、強制終了する。特に何の目当てもなくとりあえず立ち上がった。毛布は持ったまま。思いつきで、毛布を肩にかけてみた。暖かい。肩掛けです、って言ってもそんなに変じゃない気がする。これは新しい発見だ。あったかくなったので外に出ることにした。
とはいっても当てはないので、玄関を出た瞬間に後悔した。寒い。かぜがつめたい。足元をかさかさと枯葉が風に流れ去っていく。見た目からして寒々しい。もう少しで日が隠れてしまう時間だし、寒いのはあたりまえなんだけど。でも寒いなあと肩にかけた毛布を顔に寄せた。毛布に埋もれたような格好でふらふらと歩く。家の前の道をいちばん慣れた方向に歩き、車がうるさくないほうへと流されていくと、結局さっきのスーパーへ行く道を辿っていた。でも日に三度もスーパーへ向かうのは癪だと思ったので、スーパーに着かないように立ち止まった。
そこは丁度橋の袂で、とりあえず橋の真ん中まで歩いた。川は東から西に流れているらしく、下流のほうに真っ赤な太陽が見えた。紅い陽からオレンジ色の空を辿って、蒼っぽい空高くの場所をぽかんと見上げる。うっすらと雲が浮かんで、雲に紛れるように白い月があった。星はまだ見えない。
その風景の中のどの光を見つめても、ちっとも眩しくならなかった。薄暗い。だけども風景全体としては夏の真昼よりも眩しかった。もうちょっとで目を灼かれそうなくらいだ。静かで、ツンと澄んでいる。鼻の奥が熱くなって、眼からなにか零れそうな冬。今日この日のはずなのに、いつか遠くの日としての今日をみているような。
クリスマスは見えないのに、オレンジ色の世界はあまりにも上等すぎた。いかにもあったかそうで、やさしそうで、おだやかそうなのに、寒すぎる。あんまりさみしいじゃないか。
――だって、帰ってこなかったらどうしよう。
急にさっきのうたたねで見た夢が甦ってきた。右手どうし握ったはずの握手が、いつのまにか左手に摩り替わる。戸惑っているうちに現実が小さくほころびだし、急速に広がるほつれはやがて大きな穴になってぱっくりと口を開ける。世界が口を開いたら、きっと中は夕焼け色だ。私を飲み込んだ世界は、静かに存続し、私のいないことに誰も気付かないままで、クリスマスの歌がながれつづける。
――そもそもどうしてこんな日にあのひとの帰りを待っているのだか。クリスマスじゃないふつうの日ですらろくに待てないのに、どうして今日なら待てるとか待とうとか思いついたのだか。
クリスマスのあたたかさは、夢の中の握手に似ていた。しっかり握って、あったかくて、忘れがたいのに、すぐにはなさなきゃいけない。そんなつもりじゃなくたって、別れの挨拶に摩り替わってしまう。
結局、ずっと橋の真ん中で日が沈むのを見ていた。宵の明星が輝きだしても、すっかり真っ暗になった空に知らない星座がたくさん並んでも、なんとなくそこから動けなかった。
あのひとの声が聞こえたのは、むかし学校で習った北極星の見つけ方を初めて実践していたときだった。あれが北斗七星で、ここの辺を5倍にしたあたり……いや、4倍だったろうかと北の空を数えていると、後ろから聞きなれた声が飛び込んできた。考える前に振り向いて、考える前に喋っていた。
「あ、ごめん、鍵かけずにきちゃった。はやくもどらなきゃ。」
彼は驚いたようだった。全く考えてもいなかった妙にまともな台詞に、自分でも驚いた。
「えっと、鍵はどうでもいいか。でも寒いしはやく帰ろうよ。ていうか何でこんなとこにいるの」
言ってから思い出した。「そうかここ普通にあんたの帰り道なんだっけ」。
彼は苦笑している。恥ずかしくなってきて、目を逸らした。気にしてなかったけど、そういえば私はけっこう変な格好で橋の真ん中に立っている。なんで毛布なんかかぶってきちゃってるんだ。肩掛けというのはちょっと苦しいだろ。部屋の中なら許されるかもしれないけどここは公道のどまんなかで、目の前に立ってる人は完璧にシックな仕事スタイルなのに。おとなしく家でテレビみてればよかった!
急にぐるぐると羞恥が渦巻きだした私を面白そうに眺め、彼は鞄を左にもちかえながら言った。
「そうだな、寒いし早く帰ろう。」
クスクス笑いが混ざったような緩やかな声だった。私はうんと頷いて、彼の隣に並んで歩き出す。毛布は肩から外して胸に抱えることにした。さむい。でも恥ずかしさよりはましな気がする。
「ゆうごはん買ったよ。チキンとケーキとグラタン。あんまりおいしくなさそうなやつ。」
「なんだ、おいしくなさそうなのを買ったのか?」
可笑しそうだけど怪訝そうだ。たしかにもっともだと思う。自分でもちょっと迷いはある。だけどさ、
「だってそっちのほうがクリスマスっぽかったから。」
「なるほど」
おいしさより季節感をとるとは珍しいな、と笑う彼の楽しげなかんじにふわふわと引き寄せられるようにして、私はスーパーマーケットのクリスマス装飾がいかにも安っぽかったとか、ケーキ屋に達筆なカタカナで《メリークリスマス》と書かれた幕が垂れていたとかいう話を繰り広げた。丁寧に相槌を打ってくれるものだから、調子に乗ってテレビでラスト・クリスマスを歌っていたアイドルはあんまり好みじゃないとかいう話までしてしまって、また恥ずかしくなってなぜか次はラスト・クリスマスの歌詞の話を始める。
「あの曲毎年聞いてるのにさ、アイ・ゲイブ・ユー・マイ・ハートってとこしか歌詞が覚えらんないや。わたしはあなたにわたしのこころをあげました、って直訳するとすっごい恥ずかしい。そういえばハートだから心臓って訳してもいいんだっけ。でも心臓じゃ突然ホラーになっちゃうな。」
無駄な饒舌を誤魔化すように、胸元にゆれる毛糸玉を弄りながらそこまで喋ってふと気付く。この毛糸玉はなんだ。そういえば首元があったかい。自分の首にいつの間にか見慣れない白いふわふわが巻かれている!
「なにこれ?」
「マフラー。」
彼の答えは端的だった。白くてふわふわしてて、ぼんぼりまでついている、このマフラーは明らかに彼のものではなく、私の持ち物でもなく、ということはあれだ。クリスマスだ。
「ありがとう。ごめん。」
彼に倣って端的に答えてみた。でも彼は首をかしげている。察しの悪いやつ。
「マフラーとかそういうの、何も用意してなかった。ごめん。」
そこまで言ってやって初めて、ああそういうことか、という顔をする。
「こちらこそありがとうと言わないとね。クリスマスっぽいご馳走を買ってきてくれたんだろう。」
別に、ただそれっぽいだけでご馳走なんて程のもんじゃない。というようなことを言い訳しようと顔を上げたのに、結局私は「どういたしまして」と呟いただけだった。なんとなく、視線が合うとそうなってしまった。そして言い訳の代わりに、私は次のような事を話した。
――来年のクリスマスは、家の中で待っていようと思う。たぶんすごく退屈するから、なにかクリスマスっぽいメニューを作ってみたりして暇を潰せばいいのではないだろうか。でもローストチキンまでがんばる気はないから、来年もあそこのスーパーで照り焼き風ローストチキンを買う。あんたが仕事帰りにケーキを受け取って帰れるように、街のほうのケーキ屋に予約を入れるのもいいかもしれない。
そのときは「楽しみだな」と微笑んだだけだった彼が、静かに私の名を呼んだのは、オーブンレンジの前で冷凍グラタンが温まるのを待っている時だった。
「待っていてくれて嬉しい。明日はクリスマスじゃないけれど、たぶん早く帰れそうだから――」
続きは言われなくてもわかった。でも彼はやめなかった。
「待っていてくれるかな。」
いちばん肝心なところを彼はいちばん小さな声で言ったので、私は耳を澄まして全力でそれを聞き届けた。聞いたので、答える。
「じゃああしたは、クリスマスっぽくないなにか普通の夕ご飯にする。」
ありがとう、と答える声も、やっぱりさっきと同じくらいいちばん小さかった。オレンジ色の悪夢でも、I gave you my heart でも、なんだって溶かしこめそうな声だと思った。
帰れそうだと彼が言うなら、待っていて欲しいとこの声が言うなら、帰ってこないかもしれなくても、何で待ち始めたんだろうと悔やみながらでも、私はきっと待つのだろう。
だから彼は、待っていないかもしれないなんて思わないで、帰ってくれるといい。
クリスマスに休みが取れないなんて信じられない!
そう言って詰ってみるのがいまのところの将来の夢だ。