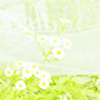家庭訪問の日、俺はいつもの車じゃなくて、普段は使わない原付で各家庭を回った。このあたりは狭い道が多いし、車を停めるスペースがあるとは限らないので、家庭訪問には自転車か原付がいい。最近は駐車違反の取締りが厳しくなっているからなおさらだ。これも、件のベテラン先生の教えである。
住宅地図を片手に、表札を確かめながら目的の家を探す。方向音痴の人はたいへんだろうな。同じ苗字の多い地区では、半分賭けのような感じで突撃することもあるけど、尋ねれば親切に教えてもらえるからそんなに大変なことにはならない。一軒に使う時間は、移動も含めて十五分。話が弾みすぎて時間が押し、ずれ込んでいくのが俺の毎年のパターンだ。
だから今年も、最後のお宅に伺ったのは予定より四十分もあとだった。表札に「糸瀬」とあるのを確かめて、門のところでインターホンを押す。白い壁の大きな洋風の家だ。生垣には燈台躑躅(ドウダンツツジ)の白い花。門の向こうに見えるのは、花水木、小手鞠、白木蓮、八重山吹。
「ごめんください、紺野です。遅くなってしまって申しわけありません。」
インターホンで声をかけると、「ご苦労様です。どうぞお入りください」とやわらかい女性の声が返ってくる。門をくぐり、玄関まで歩いて、プランターがたくさん並んでいるのがわかった。チューリップ、ライラック、雛罌粟、鈴蘭。ゆっくりと玄関の戸が開く。
「先生、今日は勝手を言いまして申し訳ございません」
きれいな女性が、玄関先で頭を下げている。緩くパーマをかけた髪は後ろでまとめられ、柔らかそうな木綿のワンピースは落ち着いた桜色。
「いいえ、とんでもありません。」
今日一日あちこちのお宅で交わしたのと同じ挨拶をほとんど条件反射で返しながら、家の中に通してもらう。リネンのスリッパには水玉模様の縁取りがあった。もしかしたら手作りかもしれない。そう思わせる雰囲気をもった家だ。子供の家庭環境を知るために、訪問のときは家の中の片付き方を確かめるようにしているけれど、ヒロヤくんのお宅はインテリアに気を遣った、このあたりには珍しいタイプである。
「どうぞおかけください」
応接間のソファを勧められ、礼を述べて掛けさせてもらう。彼女は一度部屋を出ていった。きっとお茶の用意に行ったのだろう。「おかまいなく」と声をかけるけれど、彼女はお盆を持って戻ってきた。勿忘草のティーカップとソーサー、シフォンケーキののったお皿は真っ白い。お茶とお菓子を出すと、彼女は正面のソファにきちんと脚をそろえて座り、にっこり微笑む。何か言おうとする気配が無いので、こちらからヒロヤくんの学校での様子を一通り聞いてもらった。
おとなしくて、あまり表情の変わらない子ですが、お友達はたくさんいるようですね。休み時間はいつもグラウンドに出ていますし、教室でもよく子供たちに囲まれていすよ。授業中は自分から発言するようなことは少ないですけど、私の指示にはよく従ってくれますし、授業の内容もきちんと理解しているようですから、こちらとしては特に心配なことはありません。
ヒロヤくんのお母さんは嬉しそうに俺の話を聴いていた。「安心しました」と顔をほころばせる。理想的なお母さんだ。そして、理想的な奥さん。家庭的で、品のいい。
ああいけない。ちょっと油断すると、ヒロヤくんのことより彼女のほうに意識が奪われてしまう。俺は努めて何も考えないようにした。それぞれの場面で適切な台詞を、機械的に吐き出さなければ。家の中に残る彼の気配を、探したりしてはいけない。あいつの好きな色、好きな花、好みのデザイン。見つけたって、この女性の行き届いた心配りに感嘆するくらいしか、俺にできることはない。
「ゆっくり話したいということでしたが、なにか心配事がおありですか?」
「あの、心配事というか。このあいだの授業参観のことなんですけれど」
俺は少し動揺した。紅茶をいただいて一呼吸置いてから言う。
「お父さんがおいでになってましたね。ヒロヤくんにそっくりの。ヒロヤくんはうれしそうで、いつもよりはりきってくれていましたけど、どうかなさいましたか」
「ええ、あの……」
彼女は言いにくそうに視線を逸らし、ワンピースの裾をいじっていた。内心ではおそらく彼女以上に緊張した俺がじっと待っていると、やがて小さく溜息をつき、深呼吸する。俺が「なんでもおっしゃってください」と促して、ヒロヤくんのお母さんはようやく口を開いた。
「夫が来たとヒロヤに聞いて、わたし、びっくりしてしまって」
参観日、ほんとうはわたしが行くはずだったんです。でも当日になって親類のお手伝いにいかなくてはいけなくなって。不幸があったものですから。それで、あの、ヒロヤは知らずに学校へ行ったので、さぞがっかりしたろうと思っていたんです。なのに、家へ帰ってみると、あの子、めずらしいくらいはしゃいでいて。
嬉しそうに、「お父さんが来てくれた」と言うんです。もう、ほんとうに驚きました。
結婚したときからそうなんですが、夫は、あまり家族に関心が無くて、家のことも子育てもほとんどわたし任せなんです。帰りも遅いですし、休みの日にどこかへ連れて行ってくれるということもなくて。特に冷たくあしらわれるということはありませんが、自分から何かを言い出すとか、したがるいうことが全くないんです。
入学式もわたし独りで行って、それはいいんですけど、あの子がどうだったとか話しても興味がないようで、生返事しか返って来ません。担任の先生の名前さえちゃんと聞いてくれなくって、入学して二週間もしてから、思いついたように尋ねられました。
なにもかもそんな調子で、すべてをただ義務感でやっているような、そんな感じをヒロヤも敏感に察して、さみしそうにしています。わたし、あの子がかわいそうで。なんとかヒロヤやわたしに注意を向けようと、いろいろと努力してはみたのですけれど、夫はずっと変わりませんでした。
そんなひとが、会社を早引けして授業参観に行ったというんです。
本当に嬉しくなりました。おうちのなかでは前と何も変わりませんし、参観のようすも突然行く気になった理由も、何も話してくれませんけど。それでもただ、ひとこと、先生のことを話してくれました。
――やさしいひとなんだ。とても。
「それでわたし、先生に、すごく会ってみたくなって。できれば、ゆっくりお話してみたいと思って。」
彼女は、やわらかな微笑を浮かべて、話を結んだ。幸せそうに俺を見ている。夫の変化がさぞ嬉しかったのだろう。俺は、申し訳ない気持ちでいっぱいだった。何も知らないこのひとが、無邪気に喜んでいることが、胸に痛い。
そうだったんですかと頷きながら、俺は自分がものすごくおかしな格好をして、場違いなところいるような感覚に囚われていた。灰色のスーツと、きつく締めたネクタイ。応接用ソファに、来客用のティーカップ。こんな格好で、こんな場所にいてはいけない気がした。
「あの、糸瀬さん」
「はい、なんでしょう。」
彼女は、笑顔のまま首をかしげてみせた。こういうしぐさ、ヒロヤくんもしていたっけ。俺は、ネクタイを緩めながら尋ねる。
「旦那さんは、ご在宅ですか」
彼にいてほしいような、ほしくないような、はっきりしない自分に苦笑がこみあげてくる。この期に及んでどうしようもない。
「ええ、今日はどうしたんでしょうね、とくべつ帰りが早かったんですよ。せっかくだから先生に会うか、と言っても、何も言わないで書斎へ引っ込んでしまったのですけど。」
ああ奥さん。申し訳ないけど、あなたの旦那とヒロヤくんの話はできないだろう。俺は、あいつを「糸瀬さん」なんて呼ばない。あいつにも、「先生」なんて呼ばせない。
「お会いになりますか。いま呼んでまいりますね」
いそいそと腰を浮かしかけるひとに心のうちで謝罪しながら、俺はネクタイをすっかり外し、立ち上がる。
いいえ、奥さん。俺が行きます。