
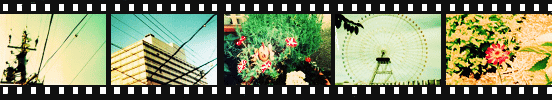
こんな夢を見た。
問18.44におけるy=a(x-p)2+qが、なだらかな弧を描く逆向きの放物線であることを確かめたところで、隆也はいったん手を止めた。これで参考書10ページ分を解いたことになる。
壁の時計を見上げると、昼と夕方の間だった。予定よりもかなり余裕がある。
この夏休み、隆也は勉強の楽しさに目覚めていた。
全てが自分の予定通りに進み、自分の努力次第で結果が出るのはいいものだ、と彼は思う。
勉強は楽だ――満足も後悔も、すべて納得ずくで進んでゆくから。
こんなふうに完全な無傷で、何の痛みも負わずにできる「努力」があることを、彼は野球を辞めるまで知らなかった。
――高校入学を機に野球を辞めたのは、正解だった。幾度もそう独りごちるのを、まるで言い聞かせるようだと、隆也は気付かないようにしている。
さて、数学が早く終わった分は、苦手な古文の時間に回すとして、まずはちょっと休憩しよう。
隆也は問題集を閉じて立ち上がり、数時間ぶりに机の前を離れた。
とりあえず台所に下りて麦茶でも飲もうと、クーラーは付けっ放しで、部屋のドアを開ける。
勢いよく扉を開けた途端、むっと暑い空気が押し寄せて、身体じゅうに纏わりついた。境界線が分かりそうなほど極端な温度差は、同じ家の中だとはとても思えないほどだ。
クーラーに冷やされていた彼の身体は、一瞬で熱を帯びてじっとりと汗をにじませる。
窓からの直射日光のせいだろうか、二階の廊下は炎天下そのもので、それはまるで、グラウンドのど真ん中にでも立っているようなありさまだった。
クラリと眩む頭がなにを甦らせているのか考えないように、ことさら冷房の有難味だけを意識して、階段を下りかけると、追い打ちのように階下からテレビの音声が漏れ聞こえてきた。居間に弟がいるらしい。弟はまた冷房もつけないで、戸を開け放しにして高校野球を見ているのだろう。
隆也の弟はかつて彼自身がそうだったように野球少年だから、こんなふうに暑すぎるときでも冷房はつけない。
扇風機一つで時間の許す限り甲子園中継に見入っているのは毎年のことで、去年までは隆也も弟の横で扇風機を奪い合っていた。
けれども今夏は階下から、あの独特のざわめきだけが熱気とともに立ち上ってくる。
その音声が周囲の空気の色を塗り替えていくような気がして、ぞくりとした。
隆也は熱い空気をかき分けるようにして、階段を一段ずつ下りる。
一歩を踏むごとに、テレビの音声はよりはっきりと、より大きくなっていった。
ノイズのようだったどよめきは、スタンドいっぱいの大観衆の歓声に変わる。
渦巻く空気のうねりは、応援団のブラスバンドになって、この蒸し暑い階段にも威勢よく鳴り響く。
夏が来るたびにテレビの中に繰り返されてきた、知りもしないのに馴染んだ音だった。
「よし、あとワンナウト!」
そこに、居間にいる弟の声援がかぶさる。
弟は基本的にバッター贔屓のくせに、今回ばかりは投手を応援しているらしい。
となれば第二試合だろう。あのひとが投げているなら当然だ。九回裏ツーアウト、となぜか隆也は確信していた。
うねるブラスバンドのなかに、コンバットマーチは聞こえない。
やがて場内アナウンスが、知らない高校の知らない打者の名を伝えた。
そして、実況のアナウンサーは、聞きおぼえのある高校名と、あの、痛いほど知っている、その実たいして何も知らない、あの投手の名まえを呼ぶ。
隆也はその名を繰り返さない。何と呼び棄てても、今よりずっと子どもだったころの、馬鹿な熱病がフラッシュ・バックしそうだからだ。
どうせ、その名を聴き取ってしまったらもう、彼は逃げられない。
真夏の陽光の下、アフリカン・シンフォニーがとぐろを巻いて隆也を捕えた。
あれっきり空っぽになった心臓に、馴染みのざわめきが過去からの反響を巻き込んでこだまする。
ランナーはいない。嬉しいのか、悔しいのか、あるいはもっと別の感情なのか、分からないまま鷲掴みにされる。満足も後悔も納得ずくの優しい時代は、とうの昔に、あのひとが攫ってしまったことを、隆也は痛みと共に思い返していた。
――痛くてもいい。この手の中にあるなら、痛くてもよかった。
いよいよ、悲鳴のような歓声が大きくなる。
隆也は堪えきれず目を瞑った。
九回裏ツーアウト。
マウンド上の投手は疲れを見せながらも負けず嫌いの顔をして、次のサインを待っている。
相対する捕手は間を置かず、迷いなくサインを出し、ミットを構える。
あいつはそれを、あの鋭い眼光で舐める。
そして、軽く頷いて振りかぶる。
首はいちども振らなかった。
そういった全てのことを、隆也は遠くの階段の途中に立って、弟の見ているテレビから聴く。
脳裏にちらつく空想上の画面の中では、あいつの眼はあのころのまま荒んでいる。そのくせ、マスク越しの捕手の顔は今の自分だった。
――無傷の「努力」なんて、そんなの、夢か、ただの暇つぶしじゃないか。
暫くして、アフリカン・シンフォニーが止んだ時、隆也は手に放物線の端を握っていた。
なだらかな下向きの弧、その幻が、いまもふたりの左手を繋いで、18.44mを問い続ける。