
no.168 Untitled ( A Swan Lake )
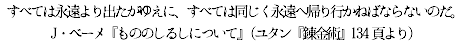
* * * * *
駅の窓口で、東の涯にある小さな町の名を告げ、係員の白手袋に硬貨を何枚か落とす。
ドゴール帽の下で手の上の硬貨を胡散臭そうに眺めた係員は、釣銭箱から銅貨を二枚、私の手に押し付けると、薄い抽斗の沢山並んだうちの一つを開けて、黄ばんだ紙片を取り出し、机上にあった小さな機械を噛ませて何かの刻印をした。
手許に視線を落としたまま係員は、トランプほどの大きさの紙片、行き先までの切符であろうそれを、片手で差し出す。私が受け取るや否や、「次の方!」初めて声を出して云った。
追い払われたような気分で、私は切符と釣銭を外套の衣嚢に突っ込むと、足下の旅行鞄を持ち上げる。隙間だらけの鞄の中で洋墨壺が転がって、からからと音を立てた。
その音を聴きつけたわけでもなかろうが、どこからともなくしゃがれた声が「お荷物、お預かり」と来る。
見れば案の定、にやにやした顔つきの赤帽が寄ってきて、旅行鞄に手を伸ばしてくる。使い込まれた四角い旅行鞄は態々預けるほど大層なものでもないというのに、昨今は不景気なのか、何でもかでも預かりたがるので困る。
赤帽と出来るだけ眼を合わさずに通り過ぎ、乗り場に急ぐと、汽車は既に停車している。
傍では子供の群れがはしゃいでいて、チョコレート菓子にでも齧り付くような真剣さでもって、黒びかりする車体をべたべたと撫でていた。私の腰ほどの背の高さの彼らが幾つくらいなのか、見当はつかなかったが、私があの子らほどの年の頃は、汽車など間近で見たことはなかったとは思う。
十二のとき、初めて乗ったのは夜汽車だったが、吐息で曇った窓には自分自身の昏い顔付と、向いの乗客の煙草の火ばかりが映っていて、外で絶えず啼いている鳥の姿が見つけられなかったのが不満だった。
詮無い回想は曇天に塞がれたようにぐずぐずと更けてゆきかけるが、とりたてて感傷的になることでもなく、耳の奥に白鳥の鳴き声をよみがえらせながら、私は二等客車に近い仮設階段に向かって歩いた。
子供たちの横を通り過ぎざま、黒い車体に何か、白いものが貼り付いているのが見えて、私は何となく足をとめた。小さな頭の並ぶ隙間、汽車の胴体に、トランプほどの小さな紙切れがくっついている。どうやら子どもらはそれを満足げに見上げていて、貼りついた何かは彼らの行為によるらしい。
何だろう――と思った途端、「このやろう!」、胴間声が鳴り響き、子どもの群れは一斉にわあっと声を上げ、蜘蛛の子を散らしたように逃げて行った。子どもらを追ってドタドタと走り寄って来たのはドゴール帽の似合わない太った車掌で、円い顔を真っ赤にしてかんかんに怒っている。車掌は人ごみのなかに散って行ったいたずらっ子たちを忌々しそうに睨みつけると、何かを貼りつけられた汽車を口惜しそうに見やった。
「ちくしょう、またやられた。悪餓鬼どもの、気に入りの遊びらしいんですよ」
特に訊きもしないのに、車掌はべらべらと喋り出す。
「やつらは入場券も無しにどこからともなく停車場に入り込む! それだけならまだしも、やつら、汽車の胴体に紙切れを貼りつけて喜ぶんですから性質が悪い。いまはいい薬品がありますからね、いい剥がし薬を使えばそりゃあ、綺麗に剥がれはしますがね、これがけっこう高価い、しかもひどく手間がかかるんですよ。こっちは忙しいってのに。それでなくてもですよ、神聖な車体にねえ、悪戯なんぞ。それだけでも、大変な、大変な重罪ですぞ! あんた、そう思いませんか」
はあ――と相槌を打ったが車掌は聴いておらず、まったくもう、剥がし薬をとってこなけりゃ、とぐちぐち云いながら来た方へ引き返していった。カーキ色のぱっとしない制服姿はあっという間に雑踏に消え、黒びかりする車体に貼られた何かの紙片らしきものだけがしらじらと異彩を放っている。
視線を吸い寄せられるように、私は紙片をまじまじと見つめる。
それは色刷りの銅版画で、どうやら遊び札か何からしかった。
赤と青と白と黄色、派手な縞模様の衣装を着け、頭陀袋を担いだ醜い男が、猫だか犬だか分からない獣に噛みつかれながら、こちらを振り向いている。旅の道化師か、或いはいかさま錬金術師か、といったようすの男と、画面越しに眼が合うのが不快だった。
私は、画の中の男ににやにやと嗤いかけられるのが如何とも耐え難く、殆ど無意識のうちに、手に提げていた旅行鞄から手を離していた。
鞄はゴトンと汽車のような音をたてて足下に落ち、かわりに空になった手は黒びかりする車体の、上に貼りついてにやついている醜い道化師に向かって伸びていく。
ここ数日切り忘れている爪を立てて紙片の角のところをかりかりと猫のように引っ掻いて捲り、指で抓めるくらいにすると、角から一息に剥ぎとった。
跡形もなく、という訳にはゆかず、剥がれ切らなかった残骸が白く醜く残ったが、剥がれて丸まった紙切れは、胡散臭い道化師の片鱗を覗かせることなく、ばらばらと崩れてモルタルの上を散っていった。
残りはさっきの太った車掌が綺麗に剥ぎ取ってくれるだろう、というところで満足し、私は置き去っていた旅行鞄をからから鳴らしながら持ち上げる。
今度こそ仮設階段に急いだ。
薔薇香水の匂い漂う一帯、一等客車の金持ちどもの脇をすり抜けていくと、二等に乗り込む階段は時計塔の真正面だった。
深緑に塗られた立派な柱が天井近くまで伸びる、その途中に円い文字盤が刳り貫かれており、豪奢な満月のような銀色の盤のうえを、十二の数字が廻り、長短の針が忙しなく動いて、それがなぜか、でたらめな時刻を指している。時計が云うには、今は午前零時らしい。
壊れた時計を見上げながら、仮設階段の頼りないステップを上ってゆくと、プラットフォームの奥のほうから、【故障中】の文字がふらつきながら近づいてくるのが見えた。それはよく見ると、大きな貼紙を持った若い駅員で、壊れた時計に貼りつけにきたようだったが、ちょっと歩くたびに彼方此方で呼び止められて、なかなかこちらへ近寄って来られそうにない。
駅員の先の長そうな道程を眺めながら、仮設階段を上る。
ブリキの階段は踏みしめると軽くて空々しい跫音をさせ、自分がまるで、玩具の兵隊にでもなったような、ろくでもない心地がした。耳の奥で、すがたの見えない白鳥の鳴き声が汽車の窓硝子に反射し、私はふらつきながら、二等客車によろめき入った。
* * *
二等客車は、四人掛けの客室が幾つも並んでいる。
どこもそれなりに空いているが、かといって無人の室はなく、黒髪の男と白髪の老女が独りずつ向かい合って掛けている客室を択び、会釈と共に滑り込む。
老女の隣は大層な荷物で埋まっていたので、私は男の隣に腰を下ろした。足元に旅行鞄を置くと、汽車は、唸りを上げながら動き出す。近くの客室から、子どもの歓声が漏れ聞こえたが、乗り合わせた二人は静かなものだ。会話ひとつしないところを見ると、親子にも見えた彼らは連れではないらしい。
藍色の眼を手許の手帳に眼を落した男はなにやら考えているようすだったが、老女のほうは落ち窪んだ目が開いているのかどうかすらよく分からなかった。
やがて年老いた女が船を漕ぎ出し、男が手帳を仕立てのいい上着の懐に仕舞った頃、客室のドアが音もなく開いた。
ドゴール帽を目深に被った、背の高い車掌が立っている。駅でかんかんに怒っていた太った車掌とは対照的な男で、あっちが満月男なら、こっちは言うなれば三日月といったようすの、痩せぎすで蒼白い男だった。
「切符を拝見いたします」
車掌は見かけどおりのかさかさした声で云い、神経質そうに鋏をカチャリと鳴らしながら、ハンドバッグから切符を出そうとしている女のほうへ近寄って行った。がさがさとバッグのなかを探っている皺くちゃの手を辛抱強く待つ車掌は、私がすでに外套の衣嚢から切符を取り出しても、まるで気付かぬようすで只管に老女のほうを待っていた。
融通の利かない車掌に呆れながら、私は、手の中の切符に視線を落とす。
ここの鉄道会社は他所よりも立派な乗車券を寄越す主義のようで、トランプくらいの大きさの、妙に分厚く確りした質の紙切れだった。
購ってすぐ衣嚢に突っ込んだきり見てもいなかったそれを初めてまともに手に取って、私はすぐ、首を傾げることになった。
四角い紙片の隅には、あの窓口係が捺したらしい、鉄道会社の刻印が確かに凹凸を作っていたが、普通の切符になら大抵は書かれているような内容、例えば出発地の駅名だとか到着地の駅名、運賃、発車時刻や客車の等級といった類のことが、何一つとして記されていなかったのだ。
かわりに印刷されていたのは、四色刷りの、妙に鮮やかな図像だった。
それは、黴臭いタッチの銅版画で、素人目にも模写に模写を重ねたようないい加減な代物と見える。描かれているのは崖の上に立つ若い男。男は古風で派手な格好をしており、竿の先に小さな荷をひとつ下げ、白い犬に吠え掛かられながら、左手には白薔薇らしき花を一輪持っている。
この汽車に乗り込む前、子どもらが汽車の胴体に貼りつけたあの絵札、太った車掌をかんかんに怒らせていた醜い道化師の画、それと別物ではあるが、不思議とよく似た絵だった。
道化師か錬金術師、或いは魔術師に憧れた莫迦な男――そういったふぜいの、いかにも嘘臭い佇まいの男はやはりこちらを振り向いていて、厭な感じの薄笑いを浮かべた眼と、どうにもぴたりと視線が合う。
これは何か、この鉄道会社が気に入って使っている意匠だろうか。画の中の胡散臭い笑みから逃げるように、私は紙片を裏返しにした。裏面は何の印刷もなく、ただ、黄ばんだ白紙があるだけだった。
いつの間にか老女の検札を終えていた車掌が手を伸ばしてきたので、私は切符として購入したこの紙切れを差し出した。車掌は流れ作業のように鋏を入れかけて、一瞬、ぴたりと動きを止めた。
「珍しいものをお持ちですねえ」
聴こえるか聴こえないかの、かさかさと雑音のような独り言を漏らしただけで、車掌はすぐに慣れた手つきで肩に下げた黒い蝦蟇口鞄に絵札を仕舞うと、車内発行用の切符用紙を取り出して鋏を入れ、愛想なく渡して寄越した。
車掌は最後に残った男の切符切りをそそくさとすませると儀礼的にお辞儀をして去っていき、後には、ごく当たり前の切符だけが残る。常識的で見慣れた乗車券に、私は安堵するでもなく、意味のない苛立ちを覚えた。
気晴らしに窓に目をやっても、曇った硝子に映るのは窓側に掛けた男の横顔と、男が点けた煙草の火くらいのもので、それなりに広がっているはずの景色は、曖昧にくすんだような色合しか判らなかった。
陰鬱な曇り空の下の、見えるような見えないような沼地よりも、硝子のなかで赤く燃える煙草と、その妙に甘ったるい紫煙に引きずられて、私の霞んだ視界を、見えない白鳥が横切っていく。氷の膜に思い出の降り積もるみずうみから、去ってゆく白鳥は、やがて天に昇って十字架になるんだと、十二だった私はそう信じていた。
初めて夜汽車に乗ったあの日のこと。
――白鳥は次の冬にまた来るじゃないかと、そう云ったひともいたような気がするが、それが誰だったかは分からない。紫煙に隠されて顔が見えないからだ。
私はいつの間にか眠り込んでいた。
* * *
夢現に、老女がどこかの駅で降りて行ったのは覚えている。その後、正面の二人掛けには誰か別の客が乗り込んで、また去ってゆき、何度か乗客が入れ替わったが、私とその横の男はどちらも同じくらい遠くまで行くらしいことを聞くともなしに聴きながら、私はうとうとと眠り続けていた。
「ねえ、あなたの番よ」
ごくあっさりした調子で、当然のように話しかけられ、重たかったはずの瞼が、ぱっと自然に開いた。眼を覚ますと、青く大きな瞳が二つ、私を覗き込んでいる。
はじめ老女が腰掛けていた座席には、今、学校の制服らしいものを着た少女が陣取っていた。私には年齢はよく分からないが、恐らく十二かそこらだろう。窓から差し込んだ明るい陽光に、栗色の髪を煌めかせ、何が面白いのかクスクスと笑っている。
私は寝ぼけ眼を擦りながら辺りを見回す。男は相変わらず落ち着いた様子で座っているだけだったが、窓の外の景色は、記憶にある薄曇りの沼地からすっかり一変していた。鮮やかな青い海原が窓いっぱいに広がって、それは、絵葉書にも似た景色だった。
「ねえ、ちょっと。あなたの番だったら」
しかし目の前の少女は外の風景には一切の関心が無いらしく、熱心に、何か誘いかけてくる。彼女に視線を戻すと、どうやら私はゲームに誘われているらしかった。少女は扇形に広げたカードを手にしている。
「やっとこっちを見た。ほら、あなたのための占いなのよ」
満足そうな邪気のない眼で促され、目を落とすと、私のひざの上にも裏返しの細長いカードが数枚置かれていた。それはちょうど、私が窓口で購入し、車掌が切符と交換に持ち去った、あの奇妙な絵札とそっくり同じ大きさで、魔術師の薄笑いの幻が視界の隅でにやりとした。
「二枚はもう引いたでしょう? わたしが最後の三枚目なのよ」
意味不明だが有無を言わせぬ少女に負けて、私はひざの上のカードを拾い集め、彼女に倣って扇形に広げてみる。カードは、スートも数字もばらばらの古めかしい占い札だった。
「ほら、わたしから、一枚引いてみて」
猫撫で声に誘われて、吸い寄せられるように私の手が伸びた。
どのカードにするか、うろうろと指を彷徨わせる私を、少女はクスクス笑って見ている。紅い唇をにっこりさせて私の選択を待つ、彼女はなにか性質の悪い悪戯でも考えている悪餓鬼ような、或いは、初心な男を揄う魔女のような、底意地の悪そうな笑い方をした。
その笑い声と微笑み、それが、頭のなかでどういうわけか、あの奇妙な絵の二枚と重なって見えた。いかさま錬金術師、奇妙な道化師、或いは魔術師、そんな空々しさを持つ不快で稚拙な画と、どこか同種の胡散臭さをなぜか、無邪気そうな少女にだぶらせたことに罪悪感を覚え、私は眩暈を堪えながら、やっとカードの一枚を択んだ。
少女の細い指が広げる扇形の、ちょうど真ん中の一枚、それに触れると、彼女はチェシャ猫のような顔付でニヤリと笑ったが、その時には私はもう別の選択をできずにいて、どういうわけか自分でも解らないままに、その如何にも怪しげな、間違いなくジョーカーであろう一枚を、迷わず抜き取っていた。
途端に、弾けるような嬌声が客室中に谺したので、私は面食らって、他のカードを取り落した。
すると少女はますます歓んで、最早ゲームは終わったとばかりに、大はしゃぎでカードを放り出し、抜き取った一枚だけを手にしている私を指差しては、お腹を抱えて笑い転げる。
「ゼロよ、ゼロだわ、やっぱり愚者を引いたわ!」
きゃっきゃと可笑しそうに、しかしどこか酷薄な色を浮かべ、散乱したカードの中で、少女は喝采している。
訳が分からないまま、私は、手の中に一枚だけ残ったそのカードを握り締めた。
ゼロとはなんだろう。ジョーカーのことを、彼女はゼロと呼んでいるのだろうか――訝しく思いつつも、そうではないとどこかで確信しながら、私は、トランプに似ているが明らかにトランプの一枚ではない紙片を見る。
カードのうえにあったのは、ただの文字だった。
洋墨は黒々と、しかし薄汚い印刷で、カードにはごく短い単語が刷り込まれている。
Le Fou――どこの言葉だったか。たしか、【愚者】と訳すはずの、これは、タロットのなかの一枚を指す語句だった。彼女らの言うとおり、ゼロの札だ。
「三枚ともだなんてねえ。元気を出してちょうだいね」
何物をも持たず、それでいて、総てを内包する、孤独な旅人。その図像を持つゼロの札。それが三枚。占いはまるで芳しくない現実を突きつけているらしい。
三枚の愚者。恐らくその意味はこうだ。
過去、現在、未来。お前は永遠に彷徨い続ける。
思考の渦に吸い込まれかかったときだ。不意に、ささやかな物音が耳に飛び込んできた。
燐寸を擦る微かな音――それがなぜ少女の嬌声の合間に、鮮明に聴こえたのかは分からない。
カードを握りしめたまま半ば呆然と隣を見上げると、乗り込んだ時から一緒だった男が、懐から取り出した煙草に火を点けているところだった。
我々のカード騒ぎに眼もくれない彼は、慣れた手つきで紙巻の先に燐寸の火を近づける。吸口からちょっと吸って赤く灯らせると、燐寸の火をすぐに吹き消した。泰然と自然な動作は不思議と魔術めいて、今もあたりに散らばった占い札の存在すら消してしまいそうだ。
すぐに紫煙がふわりと立ちこめ、奇妙な甘い香りが客室じゅうに充満した。
「煙草は苦手なの。やめてくださらない?」
少女は、先ほどまでの美しい嘲笑が嘘のように、不機嫌を隠そうともせず、あからさまに不快そうに眉を寄せた。刺刺しい口調はそれでも少女らしくはあったが、甘い匂いの煙草よりも、この男自身を嫌っているかのような口ぶりに感じられる。
彼の吸う見慣れない意匠の紙巻煙草、これはいったい何の銘柄なのか分からないが、占い師の焚く香のような匂いがするものを、少女がまさか嫌うはずがない、と私は奇妙な確信を抱いていた。
「これは失礼。御嬢さん」
男は、藍色の眼を眇め、僅かに怒りを込めた目付きで少女を見た。長く乗り合わせて初めてまじまじと見た男の顔付は落ち着きに満ちて、口元には穏やかな笑みさえ浮かべている。私の視線に気づくと、彼は目許を和ませて、ふう、と甘い紫煙を一息吐き出して訊ねた。
「貴方、その紙切れを頂いてもよろしいかな?」
火の点いた煙草を持った男が指しているのは、Le Fou と記されたトランプ大の紙切れである。辺りには、私と少女が投げ出したたくさんの占い札が、まるで奇術師の公演後の舞台ように、とりどりに散らばっているが、そちらには用はないらしい。
「はあ――どうぞ」
考えるより先に手が動き、私はゼロの札を見知らぬ男に差し出していた。
白い紙面、黒々とした印刷の、ろくでもないカードを彼は満足げに受け取って、恭しく礼を述べた。少女はずっと彼を睨んでいるが、男を止めることは出来ないものらしく、黙ってその挙動を見守っている。
左手で火のついた煙草、右手でゼロの札を手にした男は、仕立てのいい黒い上着も相まって、まさしく奇術師そのものに見えた。
それらしい杖も秘密の呪文もなかったが、男が煙草の火を札のほうにゆっくりと動かしていく、その仕種、紫に煙るゆらめきが棚引くさま、そして、赤い火が再び曇りはじめた硝子に映る煌めき、全て、なにもかもが手品――否、古い魔術か錬金術実験のようだ。
彼は、そのまま、点った火を右手のカードに近づける。
【愚者】すなわち【Le Fou】と印字された二つめの大文字、Fの真ん中のあたりで火を、紙面に押し付け、グイと擦りつける。少女がアッと声を上げたのと同時に、Fの文字はすぐに黒く焼け焦げて穴が開き、次の瞬間には橙色の焔が舌を伸ばし、紙面全体をちろちろと這って行った。
大文字のFから小文字のo、u、左にはeにL、無論残りの白紙の隅々にも、火はすぐに辿り着いてすべてを黒く、粉々にして散らしていく。小さな紙面を縦横に駆けるその焔が彼の右の指先を舐めそうになった頃、男はフッと息を吹きかけて、まるで生きているようだった不思議な火を呆気なく消してしまった。
奇妙なことに、橙色の火が消えてしまうと、燃え付きたカードの名残らしきものは、あたりを見廻しても灰一つ無く、左手に持っていたはずの吸いかけの煙草さえ、いつの間にか消失していた。
そればかりか、散乱していたはずの沢山の占い札までが、魔法のように消え去ったうえ、男をいつまでも睨みあげていた制服の少女の姿が忽然と消えている。
* * *
正面の二人掛けは、まるで初めから誰も座っていなかったかのようだ。
隣の男までも消えてしまったのではないかと疑って、確認するように横を見上げると、彼はまだそこにいて、私の懸念を読み取ったかのように可笑しげな顔をした。
「大丈夫。消えはしないから、安心なさい」
「――以前どこかでお会いしましたか?」
まるで古い知り合いか、その子どもを見るような、懐かしげな藍色の眼差しに、浮かんだ問いを私はそのまま口にのぼらせていた。彼の、年齢の読み取れない端正な顔に慥かな見覚えは無かったが、問うことは避けられぬ義務のような気がした。
彼は、訊ねたことを後悔しはじめる少し前、よくよく気を付けていないと分からないほど、ほんの僅かの動作で頷いて是を示した。
「お眠りになるといい。次は、別の形でお会いしよう」
どこで会ったのだかまるで思い出せない知り合いは、奇妙な言葉を残したきり沈黙し、幕引きとばかりに、窓に備え付けられたカーテンを引いた。
硝子の中に浮かんでいた彼の横顔は煙草の火を吹き消した時のように呆気なく掻き消え、緞帳に似た真紅のカーテンの襞が汽車の振動に合わせて揺れる。
どうやら、線路は長いトンネルに差しかかかったらしい。汽車は空洞の中を轟轟と唸りを上げて進み、トンネル内に反響させながら疾走していくが、二人きり並んで腰かけた四人掛け客室は、奇妙な静寂に満ちていた。
隣の彼はもう私の方を見ようとはせず、再び懐から手帳を取り出し、また何事か考え込んでいる。私はゆっくりと深呼吸して座席に深く座り直し、観念して目を瞑る。先ほどの、彼の言葉が呪文だったとでもいうのか、急に眠気がこみあげてきていた。
――隣に座っている男が誰だったのか思い出したのは、結局、眠りの中に沈み込んで行かんとする、まさに最後の瞬間のことだった。彼が彼であることを思い出せば、あとは自然と、私が今ここにこうしているこれは夢だということにも思い当たった。
だからもう、無理に眼を開けて、名前を呼ぼうとは思わなかった。
それよりも、次の停車場で、綺麗な絵葉書を購うほうがいい。