#11 硝子製の詩と女王さま
長い話を終えたキティに、ドロシーはカップに残った乳を差し出しました。もうすっかり冷めていましたが、キティはおいしそうに飲み干します。
「ありがとうドロシーさん。たくさん話してしまってごめんなさいね。」
ドロシーは、とんでもないと首をふります。
「すごくおもしろいお話だったわ。いろいろ謎がとけた気分よ。」
「それならよかった。」
キティはにっこりほほえんで立ち上がりました。エプロンのポケットから円い銀のお盆をとりだして、空になったカップとお皿を載せながら、黒猫のかたちをした柱時計を見上げます。
「あら、もうこんな時間になってしまったのね。ドロシーさん、汽車の時間はだいじょうぶ?」
自分の用事のことをすっかり忘れていたドロシーですが、キティにたずねられてあわてて時計を見ました。時計は、《Oz》に降り立ってから二時間と四十分をさしています。
「いけない、二十分後の汽車に乗らなきゃ!鏡の塔の女王さまにごあいさつに行くのよ。」
「鏡の塔の女王さま?いったいなんのごあいさつなのかしら?」
キティは、なぜかとても驚いた顔でたずねました。ドロシーはふしぎに思いながら答えます。
「塔の女王さまとは、おうちにある大鏡、ブルーレースというんだけど、それをとおしてよくお話しするのよ。本の貸し借りもしていて、きょうはこのあいだ借りた硝子の詩集をお返ししにうかがうの。いつもは鏡ごしにやりとりするんだけど、ほんとうに会ってみるのもおもしろいし、おいしいシャーベット水を飲ませてあげるからぜひいらっしゃい、と言ってくださったの。だからわたし、ここではシャーベット水を頼まなかったのよ。」
そう言って、ドロシーは《黒猫屋》の中を見わたして、ブリキのお星さまの上にとまっていたアゾートを呼びました。赤い鳥になったトランクにすっかりなれたようすです。
アゾートはすぐに飛んできて、すこしいすを引いたドロシーのひざの上で赤いトランクになりました。ぱちんと音をたてて留め金をはずし、ふたをあけると、青のチェック地のタオルのうしろから、タロットくらいの大きさの硝子板がのぞいています。ドロシーが硝子板をとりだしたら、トランクはすぐ赤い鳥にもどって、ドロシーの肩にとまりました。
「ほら、これがその詩集。」

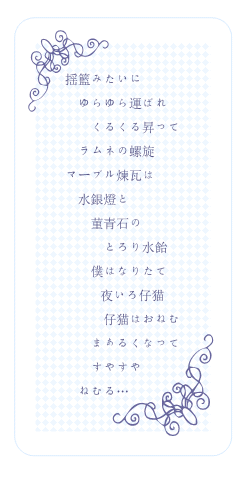
それはたったひとつの詩だったので、「詩集」といういいかたは間違いかもしれません。ドロシーは、繊細な硝子の詩をキティに差し出し、キティはそうっと受け取りました。
見ると、透きとおった二枚の硝子板のあいだに、青いレース模様と、煙のようにゆらゆらしたふしぎな詩がはさまっています。反対側は、「階段室の仔猫のための子守唄」とタイトルが書かれた表紙らしい面がありました。
文面を読んで、キティはあっと声をあげました。
「ドロシーさんが、この詩を知っていたなんて!これはさっきの黒猫さんとうさぎさんのおはなしよ。」
おどろいて叫んだキティに、こんどは、ドロシーが仰天する番でした。
「まあそうだったの?そういわれれば、黒猫さんが黒い塔の螺旋階段をくるくると運ばれる場面だわ。ああ、ちっとも知らなかった。ただ、おもしろい詩だわって思っていただけだったの。」
「鏡の塔の女王さまから借りたと言ったわね。ここには作者の名まえが書いていないけど、わたしが思うに、たぶんこれは女王が作った詩よ。」
キティは「たぶん」とは言いながら、ほとんど断言するような口調です。ドロシーはふしぎに思ってたずねました。
「あらキティ、鏡の塔の女王さまは、さっきのおはなしをご存知なの?」
きょとんとしているドロシーを前に、キティはこまったようにわらっています。なんだかはずかしそうな顔でした。
「あのね、ドロシー。黒い塔の底のお庭で、黒猫さんに錬金術師のうさぎさんのことを教えたシャーベット水調合師のおばさまのことを話したでしょう。」
ええ、そうね。と、ドロシーはうなずきました。
「おばさまは、さっき言ったとおり底のお庭を出て《黒猫屋》をはじめたのだけど、紅茶を汲みに庭へ出たついでに、うさぎさんに錬金術をおそわったり、黒猫さんの庭仕事を手伝ったりしているうちに、いつのまにか、どんどん……なんていえばいいのかしら。」
キティはここで、途方にくれたようにためいきをつきました。ドロシーは、口をはさんではいけない気がして、乳の川にいるときみたいにじっとだまっていました。
「わたしもはじめはおばさまといっしょに店にでていたんだけど、だんだんなにもかもまかされるようになったわ。おばさまは《黒猫屋》のおばさまじゃなくなって、一流の術使いになっていたの。何の術かというと、おばさま独特なんだけど、硝子とか鏡とか氷とか、透明できらきらしたのが得意みたいね。しかも、ただの術使いじゃなく、もともとの美貌とか性格とか星回りもあって、なんだかもうものすごいひとになっていて。」
ドロシーは、やっと、話の筋が読めてきました。
「気がついたら、おばさまは鏡の女王として塔で暮らしていたの。わたしも詳しいいきさつは知らないのだけど。わたしもときどき鏡ごしにお話しているわ。このあいだ、最近は鏡をめぐって可愛い女の子と友だちになるのが趣味だって言ってたっけ。」
キティはまた、おおきくためいきをつきました。ドロシーはなんていっていいか分からなくて、無言で硝子の詩をトランクの中に片付けました。
「ドロシーさん、おばさまはかわったひとだけど、おばさまのシャーベット水はとびっきりおいしいわ。わたしもまだかなわないくらい。」
なんだかとりつくろうような、キティの言い方がおかしくて、ドロシーはくすくす笑ってしまいました。
「それは楽しみね。なんなら、キティもいっしょに鏡の女王さまに会いにいく?長いこと会ってないんでしょう?」
「それはいい考え。」
キティはぱっと明るいかおになって手を叩きました。銀の髪をゆらしてうなずく楽しげなようすに、ドロシーもうきうきしてきます。
「そうと決まったら、キティ、はやく支度してのりばへ行きましょう。もう五分しかないわよ。」
「まあ大変!」
キティはエプロンを外しながら駆け出して、店の奥から三日月型のポシェットと、「Closed」の札を取ってきました。札を入り口に掛けて、ポシェットの中をたしかめると、レジスターのところからドロシーを手招きします。
「ドロシーさん、塔へは19番のりばでしょう。こっちが近道よ。」
ドロシーは、赤い鳥になったトランクを連れて、レジスターに駆け寄ります。キティは、レジスターのボタンをぱちぱち操作しています。クラブサンでも弾いているような指づかいで、ドロシーが分かったのは、さいごに「1」と「9」を押したということくらいでした。
すると、レジスターがちぃんと鳴り、開いたのは店の奥から数えて二番目にあるダイヤ形のテーブルです。天板だったはずのところが、跳ね上げ窓でも開くようにぱかっと口をあけています。
「ドロシーさん、ここを滑っていけば目の前よ。」
キティはまったくなにもおかしなことはしていない、というような穏やかな調子でにっこり笑って、ダイヤテーブルの滑り台を示して見せます。
「ええ、今行くわ。」
円テーブルの上に置きっぱなしだったコースターをポケットに入れて、ドロシーはテーブルがあけた口の中へ飛び込みました。キティもあとに続きます。
テーブルの滑り台は、あちこち枝分かれして、まるで迷路のようになっていました。でも、分かれ道はみんなふさいであるので、間違ったところについてしまうという心配はなさそうでした。キティがレジスターで操作していたのは、たぶんこの仕掛けなのでしょうが、いったいどんな魔法でこうなっているのか、見当もつきません。
(女王さまのこと、キティははずかしそうに話していたけど、わたし、キティがいつのまにか《Oz》の女王さまになっていても驚かないわ。)
そう思ったことは、キティには内緒です。
