#3 《黒猫屋》のキティ
「いらっしゃいませ、こちらへどうぞ。」
窓ぎわの円テーブルに案内してくれたのは、黒猫のバッジを白いえりもとに光らせた同い年くらいの女の子でした。
彼女は白磁にるり色で書かれたメニュー表をドロシーの前にコトリと置いて、
「キティです。どうぞよろしく。」
とほほえみかけます。それからドロシーのひざの上にあった赤いトランクをそっと持ちあげて、荷物置きの銀のかご(それは鳥かごのかたちをしていました)に入れました。すると赤いトランクは、赤い鳥になって羽ばたき、開いたままだった銀のかごから飛び出しました。

ドロシーはあっ!と叫びそうになりましたが、キティは、
「大丈夫です。必要なときには戻ってきますわ。うさぎさんの眼の色、アゾートのトランクなんですもの。」
と平然と言っては銀色の髪をさらりとゆらしてうなずいてみせるので、ドロシーも楽しげに飛び回る赤い鳥を信じて好きにさせてやることにして、メニュー表とにらめっこをはじめました。
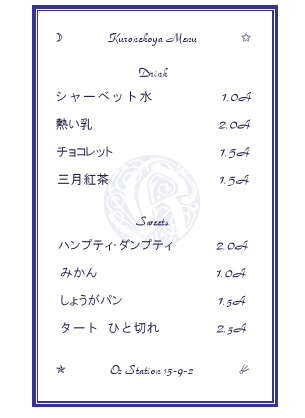
「この、Aというのはどこの都の通貨なのかしら?」
ドロシーはたずねます。
「Aは《アゾート》と読みます。《アゾートをひとしずく》という意味ですわ。」
キティは答え、ドロシーはびっくりして腰をうかしかけました。
「わたし、錬金術はできませんから、アゾートはお支払いできないわ。」
「いいえ。」
キティはゆったりとほほえんで、ドロシーを座りなおさせました。
「お客さまの赤いトランクが、もうアゾートを山ほど降らせてくれました。」
そう言って足もとに落ちていた赤い鳥の羽根をひろいあげます。羽根を持つ左手とは反対の(キティは左ききのようでした)、右手でエプロンのポケットから虹水晶の杯を取りだし、赤い羽根をぽたりと注いでみせました。すると赤い羽根はかたまりかけのジェリーのように、杯の底でまるく沈みます。こういう固体と液体の中間のようなすがたを【ダイラタント流体】というのですが、むずかしい言葉ですからドロシーはまだ知りません。
「もうこれで20アゾートはあります、おなかいっぱい注文なさったとしても、たくさんお釣りをお返ししなくては。」
言いながら杯をかかげ、キティがふちのところにキスをすると、杯は細長い試験管になります。また右手でエプロンのポケットをさぐって今度はコルク栓を取りだしたかと思うと、彼女はアゾートの入った試験管にコルク栓で蓋をしました。試験管を左手に持ちかえてエプロンのポケットにしまったキティは、両手をきちんと組んで言います。
「ご注文はお決まりですか?」