#6 《C》と《G》の二重らせん
気が付くと、ドロシーはありとあらゆるお花がとりどりに咲き乱れるお庭にいました。お庭と言っても建物はなく、ひろびろとした野原が続くとてもうつくしいところです。遠くには、てっぺんに雪をかぶった高い山が見えて、それよりは近い遠くには、お花とおなじくらい色とりどりの水たまりがいくつも見えました。
「あの水たまりのなかに、コーヒー沼もあるのでしょうね。」
今度は空を見上げてみましょう。お空の真ん中あたりは、夕暮れどきのほんのみじかい時間にだけ見られる、あのふしぎな紫色をしていました。そこを境目にグラデーションができていて、ドロシーから見て左側が青い昼間の空色、右側には紺碧の夜空が広がっています。昼の空ではお日さまが照り、綿のような雲もぷっかり浮いているのですが、夜空の側では三日月がつめたく光って、白く煌く大きな流れを見守っています。
「あれが、乳の川なのね。あんな高いところから乳を汲むのかしら?いったいどうやって昇るのか、キティに訊けばわかるかしら。」
天に流れる乳の白いかがやきは、なんだかとてもやさしくてやわらかそうですが、でもその白は、うさぎのしっぽほどにはふわふわしていませんでした。白いばらの花に似ています。荒れ果てた古いお屋敷で、裏庭にたった一輪だけ咲いた白ばら、そんなかんじだわ。と、ドロシーは考えていました。
「そうかい?ぼくは、白鳥に似ていると思うけれど。」
突然、後ろから声がかかって、ドロシーはびくっとしてしまいました。
「乳の川は、とうめいに澄み切った湖を滑る白鳥のようだと思わない?あんまりきれいで、繊細で、かなしいところがそっくりだ。それでいて、さわれば熱い、ってところも。」
ドロシーのおどろきなんか気にもしないで話し続けるのは、すこし年下の男の子でした。身体はやせて小さいですが、おとなびた顔つきのきれいな子です。
「きみも、川辺に立って、手に乳をすくってみるといい。それから、ひとくち飲んでみるといい。きっと白鳥に似ていると思うはずだよ。」
ドロシーは男の子にあいさつして、名まえをたずねようとなんども口をひらきかけていましたが、男の子はドロシーがなにか言いかけても平然と話し続けてちっともきいてくれませんでした。
「乳の川への近道を貸してやるから、かならず行くんだよ。」
そう言って、ドロシーの手になにか押し付けると、あっという間にどこかへ消えてしまいました。いったいなにを渡されたのかしら、と手のなかをみると、それは小さな木箱でした。蓋はなく、中に活字が二つだけ入っています。
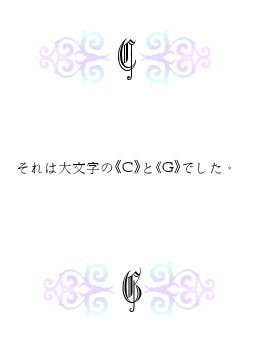
「《C》と《G》?近道だというけど、どうやって行けと言うのかしら。だいたい、あの男の子はだれだったんだろう?」
ドロシーは首をかしげ、活字をてのひらにのせてみました。ふたつとも大文字ですが、飾り文字でもなんでもないごく当たりまえの字体です。
「近道になりそうな《C》と《G》といえば……Chimera(キマイラ)とGryps(グリュプス)かしら?あるいはCassiopeia(カシオペヤ座)とGreat Bear(大ぐま座)とか。」
思いつく限りのことばを言ってみましたが、どうにもしっくり来るものがありません。もしかしてアルファベットに意味はないのかしら、とがっかりして、活字を箱に戻したとき、ドロシーはふと思いついてつぶやきました。
とたん、ふたつの活字が箱の中でかたかたとふるえだしました。ふるえがいっそうはげしくなって、急に青白く強い光をはなったかと思うと、《C》と《G》はたがいのまわりをまわりながら、夜空へ向かってくるくると昇っていきます。からみあう二つの軌跡は、小さな木箱から空のはてまで、途切れることなくつづく二重らせんの針金でした。
「これを昇っていけばいいの?」
ドロシーは木箱を足もとに置いて、おそるおそるらせんの針金に手をかけました。力なんてこめないうちに、ドロシーのからだはみるみるちいさくなって、《C》と《G》とみたいに(ただしドロシーはひとりで)くるくるまわりながら、らせんの上をすべって空高く昇っていきました。このときドロシーはただちいさくなったのではなく、《D》の活字になっていたのですが、乳の川辺についたときにはもとの大きさのいつものドロシーにもどっていたので、この先もずっと気付かないままなのでした。

↑ 「近道」をのぼる