#7 乳の川でだまりこむ
乳の川辺は、川辺よりも海辺の砂浜に似ていて、もやがかかったようにぼんやりしたところでした。砂粒のひとつひとつはとてもくっきりしてきらきらかがやいているのに、ぜんたいを見わたそうとするとまるで蜃気楼みたいにゆらいでしまいます。
おおぜい川のそばに跪いて乳を汲んでいるので、ドロシーは近くにいたご婦人に「ごきげんよう」とあいさつしました。ご婦人は、だまって首をふると、足早にさっていってしまいました。ふしぎに思ったドロシーは別のひとにもあいさつしてみましたが、だれひとり声を出しません。会釈を返してくれるひとはいるのですが、ごきげんようと声をかけてもみんななにも言わずに首をふるのです。ひとびとさえ幻のように思えて、すこしこわくなりましたが、
(ここでは、声をだしてはいけないきまりがあるのにちがいないわ。)
ドロシーは気を取り直し、乳をすくって飲んでみることにしました。
星の砂をきゅっきゅと鳴らしながら流れのすぐ近くまで歩み寄り、ひざをつきます。星の砂のとげとげがあたって、ひざがちくちく痛いはずなのですが、ドロシーのからだまでぼんやりしてしまったのか、痛いのは心臓のあたりとしか思われませんでした。
痛みにうながされるように身を乗り出せば、真珠のようにかがやく白い乳が、音もなく静かに流れておりました。乳の流れの底には、蒼や碧のひかりを持った星屑がいくつも埋もれているようでした。
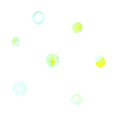
(ふしぎだわ。乳はたしかに白いのに、どうしてか底が見える。)
(男の子は、あまいと言っていたっけ。)
洋服の袖をひたしてしまわないようにたくしあげて、ドロシーはそっと両手を乳の中へ沈めます。頬で感じていたよりもずっと熱くて、その熱さだけは生き物のぬくもりによく似ていました。ちょっとでも空気にふれたらすぐに冷めてしまうような気がして、急いでくちもとに運びました。熱い乳がくちびるに触れ、ドロシーは慎重にひとくち飲みました。
(たしかにあまい。だけど、キャラメルやチョコレットとはちがうわ。)
何かのあまさに似ているように思うのですが、それが何か思い出せなかったので、もうひとくち飲んでみました。
(お菓子みたいなあまさじゃないの。なにか、もっと遠くだわ。ふわふわじゃなくて、ひりひりみたいな。だけど、それでいて、とろっとしてもいるみたいな……)
考えながら、ドロシーはすくった乳をみんな飲み干してしまいました。それでも思い出せなくて、胸がざわざわします。自分はこのあまさに似たものをかならず知っている、それだけはわかるものだからますます哀しくて、ドロシーは静かな白い乳の流れを見つめ、ながいこと考えていました。
そして、そのかなしいきもちこそが、乳のあまさにいちばん似ていると気が付くのでした。
(ほんとね、あの子のいうとおり、かなしくて熱いあまさは、ばらよりも白鳥に似ているわ。)
