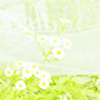小学一年生というのはどの学年よりかわいい。俺はぜったいそう思う。もちろん他の学年もそれぞれの別のかわいさがあるのだが、学校というものにちっとも慣れていない彼らを相手にするのが、小学校の先生として一番やりがいを感じるし、マイペースな子供たちが独自のやりかたでけんめいに慕ってくれるのを見ると、先生というより人としてすごく嬉しくなる。
教師という仕事が俺は好きだった。俺に向いてると言ってくれた人もたくさんいる。はじめて言われたのは、中学生のときだったかな。ある人に「せんぱいは、きっと小学校のせんせいが似合います」と言われて、それでなっちゃったようなものだけど、本当に向いてたと思う。相手のペースを尊重して助けてやるのは当時から自然にやっていたことだし、人前で喋るのは特に苦にならないし。教育実習のとき、緊張のあまり教壇で黙り込んでしまった教生がいたそうだけど、俺はこれまでそういう事態に陥ったことは無かった。
「参観は算数。とにかく算数をやっとけば安心よ!」
これは初めての授業参観を前にした教師一年生の俺に、お隣の担任だったベテラン教師が下さったありがたいお言葉だ。そのときはよくわからないまま、ベテランの先生のいうことだから、と従っていただけだったが、七年間教師をやった今、その意味がよくわかる。国語や道徳は余力があるとき。心配なら、とりあえず算数。
なぜ算数がいいかというと、国語やら道徳やらというのは、人それぞれ答えが違うのだ。子供に何か尋ねれば十人十色の答えが返ってくる。もちろんそれが国語や道徳の面白いところだけど、難しいところでもあるのだ。学校の授業ではみんなに共通の「こたえ」というものが必要だから。授業で「こたえ」を導き出す際、設定された「こたえ」と違う意見は否定しなければならなくなる場面がどうしても生まれるのだ。すごくいい意見でも、「こたえ」ではない、そういうときの「こたえ」の導き方というのはけっこう難しい。上手く納得してもらえないときは冷や汗ものだし、理屈でははっきり言えないことで自分の子供の意見が否定されるのは、親にとってあまり楽しい光景ではないだろう。
その点、算数はすごく楽だ。「こたえ」は絶対にひとつしかない。理屈で決まっていることだから、こちらとしても間違いは間違いと言いやすく、親も教師が導こうとしている「こたえ」をわきまえていてくれるから、子供の言ったことが否定されても納得できる。だから、授業参観は算数がおすすめ、というわけだ。
もちろんできそうならほかの教科をやったっていいし、俺も七年間の教師生活では色んなことをやった。一学期の参観と二学期の参観で同じ教科というのも気が引けるし。でも、今回は算数にした。久しぶりに受け持つ一年生。入学式から二週間ほどのこの時期じゃ、子供以上に親が緊張してるだろう。慎重を期すに越したことはない。
今年担任する一年二組は、男子十二人女子十二人のあわせて二十四人だから、保護者の人が後ろに立っても教室は充分に余裕がある。これは別に少人数制を採用しているわけではなく、単に少子化のあおりで一学年四十八名しかいないだけなのだが、クラスの人数が少ないのは教師にとっては助かる。田舎町の公立校らしく、生徒はたいていみんな素朴で質素なお子さんたちで、その保護者のみなさんもたいていみんな素朴で質素な方々であった。保育所や幼稚園で顔見知りのお母さん方も多く、「あらどうもこんにちは」「あら○○ちゃんのお母さん」というような挨拶があちこちで交わされている。子供たちは母親の様子を窺ったり、そわそわと扉のほうを見たりとざわついているが、マイペースなヒロヤくんが窓の外の何かを目で追っているのはいつものことだ。
「じゃあみんなも先生とおなじように、赤いおはじきを五つ並べてみましょう。」
俺が前の晩に立てた予定通りの台詞を言ったとたん、ヒロヤくんが窓の外に何かを見つけて「あっ」と叫んだ。みんなが「どうしたの」と騒ぎ出す。おっとりと口数の少ない彼が授業中に声を上げるのはめずらしいことだ。彼はまわりのおともだちに答えることも、赤いおはじきを出すこともなく、長い睫をぱちぱちと動かしている。
「はいみんな、赤いおはじき五つだよ」
どうしたのだろうと思いながら、俺はヒロヤくんのほうに声をかけた。彼の家の人は来ていないようだったけど、参観日なのであまり名前を出して注意しないほうがいいだろう。彼は、俺の声にハッとして「さんすうせっと」からおはじきを取り出す。いつになくすばやく、熱心な手つきだ。頬も赤らんで、興奮してるようだった。
その様子でなんとなくわかった。きっと窓の外にお母さんを見つけて嬉しかったんだろう。まじめに授業を受けている様子を見せて、喜んでほしいのだろう。おそらくは彼に似た色白のひとが、まもなく教室にやってくる。
俺は授業中だというのに、ヒロヤくんの母親はどんなひとだろう、はやくそのひとを見てみたい。そんな気持ちでいっぱいになっていた。彼を産んだ人なら美人だろうなとか、決してそういうやましい気持ちじゃない。ただ、ヒロヤくんは非常に独特なのだ。表情を変えず、笑顔もあまり見せてくれないが、ふわふわと独特のペースで楽しそうにしている。彼が俺を「せんせい」と呼ぶ声は、そのときは意識しないのに、あとでおもいだすとなぜかとてもやさしく響いた。
なつかしいようなその感じを、俺は知っているような気がしたけれど、あまり思い出したいと思わなかった。とにかく母親を見たい。きっと彼に似た人だ。やわらかそうな髪で、色が白くて、ぽやんとしているのに甘ったるくない。きっとそんなお母さんだ。
しかし、授業が終盤になっても、ヒロヤくんのおうちのひとは現れない。彼の様子をみればそれは明らかだ。俺の指示に懸命についていきながら、廊下側の窓や戸を窺っている。ちらちらと見て、扉が開くたびに息をつめ、がっかりして吐き出す。いったいどうしたんだろう。ヒロヤくんは一人っ子だから、兄か姉の教室を先に見ているということもないだろうに。
黒板におはじきの絵を描きながらまだ見ぬヒロヤくんの母親に気を取られていることができるのが、算数のすばらしいところだ。頭の片隅を考え事に使いながらも、授業はつつがなく進んでいた。
十個のおはじきの絵を描きおえ、「さあ」と子供たちに向き直ったときだ。
控えめな音を立てて、教室の戸が開いた。とたん、ヒロヤくんが細い歓声をあげる。
さあ、の後に用意した台詞といっしょに、浮かべた笑顔まで飛んでいった。戸のところで立ち尽くす「ヒロヤくんのおうちのひと」も、浮かべていた無表情を飛ばされてしまったようだった。長い睫をぱちぱちと瞬かせるさまは、ヒロヤくんにそっくりだった。ふわふわした髪が風に揺れている。そういえば、教室の窓を開けておいたのだった。ぽかぽかした春のやわらかい風は、子供らも大人たちもうきうきした気持ちにさせてくれるだろうと思ったから。
こんなにあったかい日に、スーツの上着まで着込んでちゃ暑いだろうに、ネクタイをきっちり締めた「彼」は、息苦しそうに俺を見つめている。上等の背広は息子そっくりのきれいな顔によく似合っているのに、なぜかひどく場違いに思えた。悲しそうに眉を顰めて、彼は自分の茶色いスーツ、ヒロヤくんの白いカッターシャツ、それから教室のカーテンが丸く膨らむ様子に目をやり、最後にロッカーの上に飾られたタンポポを見た。
そのタンポポは、今朝ヒロヤくんが摘んできてくれたのだと、知っていたのかもしれない。お父さんだもんな。花瓶では大きすぎたから、俺のマグカップに活けてやった。もう十数年使っている空色のマグカップは、むかし誕生日にもらったものだ。
覚えているか。お前がくれたんだ。
ヒロヤくんのお父さん。
彼はタンポポ――それともマグカップのほう?――から目を逸らすと、再び俺のほうに視線を移した。もうぱちぱちとまばたきはしない。入ることも去ることもできないで、泣きそうな顔をして俺を見ている。彼が人前であんなに表情を崩すのは珍しい。俺しか見たことなかったんじゃないかな。……それはうぬぼれすぎだろうか。ヒロヤくんのお母さんなら、夫のこんな顔にも驚かないのかな。
「どうぞ、遠慮なくお入りください。」
立ち尽くす彼にぎこちなく声をかけたのは、「保護者の方」に気を遣ったわけじゃない。そうでなきゃいけないんだけど。でもおまえにそう受け取られては困ってしまうよ。
彼は小さく会釈をして中に入ると、お母さん方の列の隅っこに立った。お父さんが来てくれてはしゃいでいるヒロヤくんに、前を向きなさいと合図している。頬を紅潮させたヒロヤくんがキラキラした大きな目で俺の言葉を待つ姿を見て、飛んでいった笑顔が戻ってきた。やっぱりヒロヤくんは、お父さんに良く似てる。
「さあ、黒板のおはじきはいくつあるかな?わかるひと!」
はあい、と一斉に手が上がる。ヒロヤくんもまっすぐに左手を上げている。彼は左利きなのだ。お父さんとおんなじで。
「じゃあ、ヒロヤくん」
「じゅっこ!」
元気な声が返ってくる。正解。授業中に手を上げたためしなんかないくせに、かわいいもんだ。お父さんが来たのがそんなに嬉しいかい。こころはあたたかかったけど、俺は彼のほうを見ないようにしながら授業を進めた。ヒロヤくんが彼に似ていることじゃなくて、似ていない部分を見つけてしまうことが怖かった。
もう、台詞が飛んだりはしない。彼もお母さん方とそつなく挨拶を交わしている。このあとの学級懇談会に出たとしても、俺のことを彼は「先生」と呼ぶだろう。「いつもお世話になっております」って、愛想笑いのひとつも浮かべるかもしれない。おまえが「せんぱい」って呼ぶ声が、すごく聞きたいよ。俺だっておんなじなのにな。俺だって、笑顔で挨拶するだろうに。「いいえこちらこそ、糸瀬さん」ってさ。
「いとせ」は知ってる。何度も呼んだ。たくさん笑顔を見せてもらったから。だけど、「糸瀬さん」は知らない。愛想笑いなんか、もらったことないって信じてていいかな。
彼は、学級懇談会に出ずに帰っていった。息子にだけ声をかけて、誰とも目を合わせないで出て行った。視界の隅っこで茶色い上着が遠ざかるのを捉えながら、俺は保護者の皆さんに挨拶し、懇談会はあっけなく終わった。
もうすぐ家庭訪問がある。こんどこそ「ヒロヤくんのお母さん」に会えるだろう。家庭訪問で父親が出てくることは、父子家庭でもない限り滅多にない。今日はきっと仕事の都合か何かだろうな。でも正直言って、あまりお母さんに会いたくはなかった。だって、「ヒロヤくんのお母さん」で、「糸瀬さんの奥さん」であるひとに、俺は笑顔で挨拶するのだ。「お家での様子はどうですか」。「なにか気がかりなことはありますか」。通り一遍の台詞を吐き、出てきたお茶を頂いて、お菓子を丁重に断る。何事も無かったような顔をして、私(ワタクシ)ヒロヤくんの担任でございます、と振舞う。
何事かは、確かに有るのに。俺の心の中と、過去の彼との中に。それから今の彼の中にも、少しは残っているかもしれない。
だってあいつ、泣きそうに俺を見ていたじゃないか。あれは、俺が知っている彼だった。知らない顔は、見せないで帰っていったじゃないか。
ヒロヤくんがお母さんから手紙を預かってきたのは、「家庭訪問のお知らせ」のプリントを配った二日後のことだ。手紙と言っても短いメモのようなもので、内容はごくありふれたものだった。
先生とゆっくりお話したいので、訪問の順番を最後にしてもらえませんか。無理を言って申しわけありません。
達筆で小さめの字。菫の模様の便箋だった。俺は手紙を受け取った日の晩、糸瀬さんのお家に電話をかけた。三コール目で女性が出る。はい、糸瀬でございます。
もしもし、ヒロヤくんのお母さんですか。お忙しい時間にすみません。担任の紺野です。家庭訪問の件で。ええ、ヒロヤくんから受け取りました。いいんですよ、ご心配なく。ご希望の通りにさせていただきます、また改めて日時のお知らせを配りますので。ええ。こちらこそ。よろしくお願いします。では、ごめんください。失礼します。